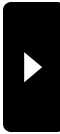2011年04月10日
レンブラント展 【国立西洋美術館】
東京・上野の国立西洋美術館まで出かけて参りました。
頭が悪いという言うか、想像力の欠如というか、震災の後だし空いているだろうと
高をくくっていました。
まず、桜がほぼ満開のせいか、上野駅周辺の人の多さに驚き、美術館に入っても
人の多さに驚きました。駅のアナウンスでは、パンダを観るのに入場制限をかけている
だとか・・・
さて、肝心のレンブラント展ですが・・・
僕はヒネクレ者なので展覧会に行くとキュレーターにはだまされないぞ!と
戦闘心を丸出しに行くのです。場合によっては揚げ足取りのようなことになり兼ねない
危険性はあります。
まあ、そこは素人なので言いたいことを言えば良いと思っています。
で、肝心のレンブラント展ですが・・・
正直に言うと、人が多すぎて雑に舐めるように観るだけでした。
ただ、展覧会の構成がつまらない!のが第一の感想です。
西洋美術の歴史は、僕なりの解釈では、マルセル・デュシャン以前と以降に分かれます。
マルセル・デュシャン以前の大きな意味での『リアリズム』は、レンブラントでほぼ完成されています。
恐らく、レンブラントが絵をキャンバスの上に再構成するプロセスの中で
ルネサンスから印象派に到るマニエールの時系列発展を試行錯誤していた
節が見られます。
芸術が『リアリズム』の範疇にある時は、科学と芸術はパラレルです。
決して人と機械というような二元論的対立概念ではありません。
その辺りの思想的な解釈は、興味があればピエール・クロソフスキーの『生きる貨幣』が
人の感覚の倒錯を冗長させる機械を分かり易く解説してくれていますので
興味のある方は是非読んでみて下さい。
まあ、なぜか日本では崇高な学術の世界で未だに人と機械の対立の二元論がまかり通る国ですから
思想のガラパゴスと固着は日本の得意とすることかもしれません。
話が広がり過ぎましたが、レンブラントはやはり西洋芸術の歴史という縦糸の中で
読み込む方が多層的で断然面白くなっていくと再確認できました。
頭が悪いという言うか、想像力の欠如というか、震災の後だし空いているだろうと
高をくくっていました。
まず、桜がほぼ満開のせいか、上野駅周辺の人の多さに驚き、美術館に入っても
人の多さに驚きました。駅のアナウンスでは、パンダを観るのに入場制限をかけている
だとか・・・
さて、肝心のレンブラント展ですが・・・
僕はヒネクレ者なので展覧会に行くとキュレーターにはだまされないぞ!と
戦闘心を丸出しに行くのです。場合によっては揚げ足取りのようなことになり兼ねない
危険性はあります。
まあ、そこは素人なので言いたいことを言えば良いと思っています。
で、肝心のレンブラント展ですが・・・
正直に言うと、人が多すぎて雑に舐めるように観るだけでした。
ただ、展覧会の構成がつまらない!のが第一の感想です。
西洋美術の歴史は、僕なりの解釈では、マルセル・デュシャン以前と以降に分かれます。
マルセル・デュシャン以前の大きな意味での『リアリズム』は、レンブラントでほぼ完成されています。
恐らく、レンブラントが絵をキャンバスの上に再構成するプロセスの中で
ルネサンスから印象派に到るマニエールの時系列発展を試行錯誤していた
節が見られます。
芸術が『リアリズム』の範疇にある時は、科学と芸術はパラレルです。
決して人と機械というような二元論的対立概念ではありません。
その辺りの思想的な解釈は、興味があればピエール・クロソフスキーの『生きる貨幣』が
人の感覚の倒錯を冗長させる機械を分かり易く解説してくれていますので
興味のある方は是非読んでみて下さい。
まあ、なぜか日本では崇高な学術の世界で未だに人と機械の対立の二元論がまかり通る国ですから
思想のガラパゴスと固着は日本の得意とすることかもしれません。
話が広がり過ぎましたが、レンブラントはやはり西洋芸術の歴史という縦糸の中で
読み込む方が多層的で断然面白くなっていくと再確認できました。
Posted by きべいち at
22:40
│Comments(0)
2011年04月03日
再び大相撲八百長問題について
約2ヶ月ぶりの更新です。
八百長に関わったとされる力士や親方などの処分が決まりましたね。
処分の結果から見ると、大相撲はこの『八百長』を伝統として残すと発表したようなものですね。
ずっと隠しておきたいというのが本音でしょう。
もし、この『八百長』が由々しき問題で無くすべきと考えるなら、罪は不問にすると明言して、
過去から現在まで洗いざらい明らかにして、『八百長』無き後の大相撲がどうあるべきかを発表するでしょう。
今回の処分に関しては、表向き世論に迎合してトカゲの尻尾切りをして体制を守ったということです。
今回の震災の後にフランスの『ル・モンド』紙が
『日本が民主主義国家というのはある程度までで、多くの決定が不明瞭な利益算段のために
行われ、また多くの分野が汚職によって生まれている』と評しています。
この言葉から想像すると、世界から見た日本は、
私達が見ている大相撲の社会のように見えるのではないかと思います。
だとするならば、この大相撲の問題は我々もまた問題を共有しているのだと気づいた方が、
社会の閉塞感を打破できるような気がします。
日本が社会も技術も制度も最も近代化しているというのは大きな勘違いで、
それぞれ独自の世界を築き上げ、
それを『近代』化に成功したと認識している錯覚から目覚めるべきです。
八百長に関わったとされる力士や親方などの処分が決まりましたね。
処分の結果から見ると、大相撲はこの『八百長』を伝統として残すと発表したようなものですね。
ずっと隠しておきたいというのが本音でしょう。
もし、この『八百長』が由々しき問題で無くすべきと考えるなら、罪は不問にすると明言して、
過去から現在まで洗いざらい明らかにして、『八百長』無き後の大相撲がどうあるべきかを発表するでしょう。
今回の処分に関しては、表向き世論に迎合してトカゲの尻尾切りをして体制を守ったということです。
今回の震災の後にフランスの『ル・モンド』紙が
『日本が民主主義国家というのはある程度までで、多くの決定が不明瞭な利益算段のために
行われ、また多くの分野が汚職によって生まれている』と評しています。
この言葉から想像すると、世界から見た日本は、
私達が見ている大相撲の社会のように見えるのではないかと思います。
だとするならば、この大相撲の問題は我々もまた問題を共有しているのだと気づいた方が、
社会の閉塞感を打破できるような気がします。
日本が社会も技術も制度も最も近代化しているというのは大きな勘違いで、
それぞれ独自の世界を築き上げ、
それを『近代』化に成功したと認識している錯覚から目覚めるべきです。
Posted by きべいち at
10:23
│Comments(0)
2011年02月10日
大相撲の八百長問題について
大変長らくブログを留守にしていた。
久しぶりに書いてもなかなか人の目に触れないのも分かっていて、ブログに書くことに決めた。
少し前からtwitterを始めたら、僕の性分ではブログよりtwitterの方が考えを気軽に出し易かった。
ブログだと書くということになり、書く前にコンセプトを固めないと書き始めることが出来なかった。
だから書きたいと思っても、コンセプトをまとめようとしている間に時間が経ち、よっぽど気になることしか書けなかった。
ということからすると、今回も気になることなのだ。
結果的にtwitterでは対応できないから、書かざると得ないということですね。
さて、標題の「大相撲の八百長問題」について・・・
単純な問題ではない。いくつか整理したい。
まず、「プロスポーツ」ということ。
それだけで二つ問題が含まれる。「プロ」とは何か?「スポーツ」とは何か?ということである。
「八百長」と言われるモラルの問題。
他には「大相撲」の文化としての側面。
もっと深い問題として、日本の社会性の問題。
ざっと挙げただけで5つの問題が含まれる。
僕の考え・・・
「スポーツ」に報酬が伴う場合、通常それを資格の問題はともかくとしてそれを「プロ」と呼んでいる。
その時点でそのプレーヤーは「見られる」し「魅せ」なければならない。
それからすると、意図を持って勝負の流れを演出することは、あっても良いと思う。
それをその業界全体で意図を持って作り出すのも然り。
結果として見る側は満足すれば、興行は成立。つまりその「プロスポーツ」は成立する。
その成立した中で勝負によって収入が変わるならば、勝負に貢献したものとして敗者への金銭の配当は当然あって自然だろう。
「見る」ということに関しては、「見られる対象(ここでは相撲)」の客観性には依存してはいないのだ。常に「見る」側の主観においてしてか成り立たないのだから、感動するのだ。そこを分からないから「見られる対象」を批判するのだが、それは主客が転倒している。
大相撲の文化としての側面を考えた場合、神事から始まっている。つまり前述した「プロスポーツ」の興行としてではなく、意図的にストーリーが組み立てられやすい土壌がある。とすると歴史性と近代的な興行性によって、勝敗が意図的に仕組まれ易いということである。
全く違った側面から今回の現象を考えたい。
今回の大相撲バッシングを捉えると日本の社会の病理にも思える部分がある。
今現在、今回の勝敗の意図的な操作とそれに伴う金銭の授受を、マスコミもそろって「八百長」として批判をした。
事の真偽や善悪の価値判断もされない段階でである。
結果的にこれがその業界に渡る慣習だったとすると、事の真偽と善悪が決まらない段階でこれだけバッシングをすると、矢面に立った当事者のみの処分で終わる。結果としてその慣習は残る。つまりとかげの尻尾きりで終わる。
むしろこのような問題が起こった場合は、事の真偽や善悪を綜合的に判断してからでないと、マスコミのアジテーションにより当事者だけを悪者に祭り上げ、結果的に何も変わらないということになる。それこそ一番の不公平ではないか?イジメに等しい。
この土壌は、結果的にもっと大きな問題になって来る。今回のケースもその可能性が高いが、意図的にリークして他に重要な問題を覆い隠す手段として使われるということである。つまり、一業界の問題にしか過ぎない当事者達は、二重に祭り上げられ、大きな被害者になる。
どなたか意見を求む。
久しぶりに書いてもなかなか人の目に触れないのも分かっていて、ブログに書くことに決めた。
少し前からtwitterを始めたら、僕の性分ではブログよりtwitterの方が考えを気軽に出し易かった。
ブログだと書くということになり、書く前にコンセプトを固めないと書き始めることが出来なかった。
だから書きたいと思っても、コンセプトをまとめようとしている間に時間が経ち、よっぽど気になることしか書けなかった。
ということからすると、今回も気になることなのだ。
結果的にtwitterでは対応できないから、書かざると得ないということですね。
さて、標題の「大相撲の八百長問題」について・・・
単純な問題ではない。いくつか整理したい。
まず、「プロスポーツ」ということ。
それだけで二つ問題が含まれる。「プロ」とは何か?「スポーツ」とは何か?ということである。
「八百長」と言われるモラルの問題。
他には「大相撲」の文化としての側面。
もっと深い問題として、日本の社会性の問題。
ざっと挙げただけで5つの問題が含まれる。
僕の考え・・・
「スポーツ」に報酬が伴う場合、通常それを資格の問題はともかくとしてそれを「プロ」と呼んでいる。
その時点でそのプレーヤーは「見られる」し「魅せ」なければならない。
それからすると、意図を持って勝負の流れを演出することは、あっても良いと思う。
それをその業界全体で意図を持って作り出すのも然り。
結果として見る側は満足すれば、興行は成立。つまりその「プロスポーツ」は成立する。
その成立した中で勝負によって収入が変わるならば、勝負に貢献したものとして敗者への金銭の配当は当然あって自然だろう。
「見る」ということに関しては、「見られる対象(ここでは相撲)」の客観性には依存してはいないのだ。常に「見る」側の主観においてしてか成り立たないのだから、感動するのだ。そこを分からないから「見られる対象」を批判するのだが、それは主客が転倒している。
大相撲の文化としての側面を考えた場合、神事から始まっている。つまり前述した「プロスポーツ」の興行としてではなく、意図的にストーリーが組み立てられやすい土壌がある。とすると歴史性と近代的な興行性によって、勝敗が意図的に仕組まれ易いということである。
全く違った側面から今回の現象を考えたい。
今回の大相撲バッシングを捉えると日本の社会の病理にも思える部分がある。
今現在、今回の勝敗の意図的な操作とそれに伴う金銭の授受を、マスコミもそろって「八百長」として批判をした。
事の真偽や善悪の価値判断もされない段階でである。
結果的にこれがその業界に渡る慣習だったとすると、事の真偽と善悪が決まらない段階でこれだけバッシングをすると、矢面に立った当事者のみの処分で終わる。結果としてその慣習は残る。つまりとかげの尻尾きりで終わる。
むしろこのような問題が起こった場合は、事の真偽や善悪を綜合的に判断してからでないと、マスコミのアジテーションにより当事者だけを悪者に祭り上げ、結果的に何も変わらないということになる。それこそ一番の不公平ではないか?イジメに等しい。
この土壌は、結果的にもっと大きな問題になって来る。今回のケースもその可能性が高いが、意図的にリークして他に重要な問題を覆い隠す手段として使われるということである。つまり、一業界の問題にしか過ぎない当事者達は、二重に祭り上げられ、大きな被害者になる。
どなたか意見を求む。
Posted by きべいち at
06:34
│Comments(0)
2009年11月20日
政治の意味
事業仕分けは法的な拘束力は無い。
ただ国の事業仕分けは国会議員が参加しているだけにその意味は軽くない。
スーパーコンピューターを始めとして多くの科学技術の予算が無駄として削られる対象になっている。
これらの予算を無駄と判断するその考えをもっと詳しく聞きたい。
最近、東洋哲学勉強会に参加している。
その教科書は『大学』
中国の儒教史上で語らずには通れない書であるが、著者は諸説様々である。
では『大学』とは何か?
それに関しても解釈が可能だが、宋の司馬光の一説を引用して政治が何たるかを言う。
「章を離ち(分かち)句を断ち疑を解き結を釈くは、これ学の小なるもの、正心・修身・斉家・治国よりもって盛徳、天下に著明なるに至るは、これ学の大なるものなり」
この言葉を借りれば、日本はあまりにも小学に偏って教育を考え、人の評価をしている。
日本の企業の海外戦略も大きなビジョンやグランドデザインを描ける人もいない。
この国の衰退はもうとっくに始まっている。
ただ国の事業仕分けは国会議員が参加しているだけにその意味は軽くない。
スーパーコンピューターを始めとして多くの科学技術の予算が無駄として削られる対象になっている。
これらの予算を無駄と判断するその考えをもっと詳しく聞きたい。
最近、東洋哲学勉強会に参加している。
その教科書は『大学』
中国の儒教史上で語らずには通れない書であるが、著者は諸説様々である。
では『大学』とは何か?
それに関しても解釈が可能だが、宋の司馬光の一説を引用して政治が何たるかを言う。
「章を離ち(分かち)句を断ち疑を解き結を釈くは、これ学の小なるもの、正心・修身・斉家・治国よりもって盛徳、天下に著明なるに至るは、これ学の大なるものなり」
この言葉を借りれば、日本はあまりにも小学に偏って教育を考え、人の評価をしている。
日本の企業の海外戦略も大きなビジョンやグランドデザインを描ける人もいない。
この国の衰退はもうとっくに始まっている。
Posted by きべいち at
00:25
│Comments(0)
2009年11月12日
馬鹿馬鹿しいにも程がある・・・【事業仕分け】
http://www.asahi.com/politics/update/1030/TKY200910300415.html
民主党が国の様々な事業で事業仕分けをしている。
それはともかくとして、航空運賃の正規運賃にケチをつけるとは馬鹿にも程がある。
飛行機の運航は、天候や状況に左右され易い。
だから割引運賃を使用することは、それだけ問題を伴う。
払い戻しができないとか、航空会社を変えられない、予約変更に追加料金がかかる等々・・・
つまり、何らかのリスク回避として正規運賃が当然なのである。
民間企業もかつては正規運賃を使用してきたが、ここ10年は割引運賃を使用する例が増えている。
そのリスク回収は、どこかで弾力的に行う。
ただ政府関係機関は、リスク回収をする仕組みや仕掛けが持てるわけではない。
だとしたら、正規運賃を使い、業務遂行を第一に考えるのが人民のための福祉にも繋がる。
浅はか以外の何ものでもない。
民主党が国の様々な事業で事業仕分けをしている。
それはともかくとして、航空運賃の正規運賃にケチをつけるとは馬鹿にも程がある。
飛行機の運航は、天候や状況に左右され易い。
だから割引運賃を使用することは、それだけ問題を伴う。
払い戻しができないとか、航空会社を変えられない、予約変更に追加料金がかかる等々・・・
つまり、何らかのリスク回避として正規運賃が当然なのである。
民間企業もかつては正規運賃を使用してきたが、ここ10年は割引運賃を使用する例が増えている。
そのリスク回収は、どこかで弾力的に行う。
ただ政府関係機関は、リスク回収をする仕組みや仕掛けが持てるわけではない。
だとしたら、正規運賃を使い、業務遂行を第一に考えるのが人民のための福祉にも繋がる。
浅はか以外の何ものでもない。
Posted by きべいち at
17:29
│Comments(0)
2009年11月12日
JALについて【その2】
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091111/biz0911111347008-n1.htm
産経からの記事だが、前にも記したようにJALの航空会社としての価値は高い。
産経からの記事だが、前にも記したようにJALの航空会社としての価値は高い。
Posted by きべいち at
05:37
│Comments(0)
2009年10月24日
JALについて
JALについて書こう。
ここ10年くらいだろうか・・・
それとも御巣鷹山の事故以来だろうか・・・
とにかく何かにつけてJALは批判の対象となってきた。
そして経営不振を迎え、公金を入れて救済されることに賛否両論あると思う。
JALとは、空港でも営業や運賃(航空運賃)の事で一緒に仕事をしてきた。
その経験から言うと、JALは残すべきだと思っている。
やはり航空会社の老舗として世界でそのスキルやノウハウはトップクラスである。
それは日本の他の航空会社がCM戦略に成功してイメージを高めているが、彼らにそのノウハウはない。
それを航空業界の何たるかを知らないマスコミが叩き続けてきた結果が、営業に響いたと感じている。
もちろん、JALにも非はある。
ただ国策会社としてかなり国の政策を受け続けてその弊害がかなり残っている。
だから早く立ち直るべきだと思うし、それを国として援助すべきだと思っている。
早くしないと貴重な人材を失い、そのノウハウの継承もままならなくなり、日本の航空業界の痛手になる。
他の会社にその力はない。
恐らく、航空業界で働いた人間ならば、それをわかるはずだ。
ここ10年くらいだろうか・・・
それとも御巣鷹山の事故以来だろうか・・・
とにかく何かにつけてJALは批判の対象となってきた。
そして経営不振を迎え、公金を入れて救済されることに賛否両論あると思う。
JALとは、空港でも営業や運賃(航空運賃)の事で一緒に仕事をしてきた。
その経験から言うと、JALは残すべきだと思っている。
やはり航空会社の老舗として世界でそのスキルやノウハウはトップクラスである。
それは日本の他の航空会社がCM戦略に成功してイメージを高めているが、彼らにそのノウハウはない。
それを航空業界の何たるかを知らないマスコミが叩き続けてきた結果が、営業に響いたと感じている。
もちろん、JALにも非はある。
ただ国策会社としてかなり国の政策を受け続けてその弊害がかなり残っている。
だから早く立ち直るべきだと思うし、それを国として援助すべきだと思っている。
早くしないと貴重な人材を失い、そのノウハウの継承もままならなくなり、日本の航空業界の痛手になる。
他の会社にその力はない。
恐らく、航空業界で働いた人間ならば、それをわかるはずだ。
Posted by きべいち at
09:06
│Comments(0)
2009年09月20日
民主党が目指すべきこと
民主党はまず『脱官僚政治』を掲げている。
そのために政治の力を強化する体制づくりを目指しているようだ。
その目玉が『国家戦略室』なるもの。
内閣に置くのだと言う。
ということは、行政府のトップということか。
一方で、民主党の政務調査会を無くすという。
では立法府である国会および国会議員の政策立案のための拠り所はどこにあるのだろう。
脱官僚政治を目指すのなら、政務調査を独自に展開し、それを元にきちんと政策立案をして
その執行だけに官僚を専念するようにするのが本来ではないか?
つまり、行政府と立法府を一緒にしてしまうということは、民主主義を逸脱しているように思えてならない。
これにより政治による独裁が制度上可能になったとも言える。
どなたか意見を下さい。
そのために政治の力を強化する体制づくりを目指しているようだ。
その目玉が『国家戦略室』なるもの。
内閣に置くのだと言う。
ということは、行政府のトップということか。
一方で、民主党の政務調査会を無くすという。
では立法府である国会および国会議員の政策立案のための拠り所はどこにあるのだろう。
脱官僚政治を目指すのなら、政務調査を独自に展開し、それを元にきちんと政策立案をして
その執行だけに官僚を専念するようにするのが本来ではないか?
つまり、行政府と立法府を一緒にしてしまうということは、民主主義を逸脱しているように思えてならない。
これにより政治による独裁が制度上可能になったとも言える。
どなたか意見を下さい。
Posted by きべいち at
19:22
│Comments(0)
2009年09月12日
水の危機
カザフスタンとウズベキスタンの国境を挟んで、アラル海という塩水湖がある。
旧ソ連時代の政策から、綿花栽培に力を入れるために上流に運河を建設したことから、急激に水量が減り始め、
現在では、1960年当時に比べて表面積で約20%にしか過ぎない。
実は私たちがコットン衣料を安価で入手できるようになった背景の一部である。
これが、先日の日記で触れたバーチャルウォーターという概念を我々が知らなければならない所以である。
我々の大量消費と使い捨てという生活文化をもっともっと見直す必要があるということ、リサイクルにある程度お金を必要として
その出費に関して責任を持つということは、少なくともバーチャルウォーターの輸入量の軽減と自然保護という観点で
我々の義務にするべきである。
そうでなくても今の我々を巡る水の状況は、水をいかに守るかということに大規模な資本投資をせざるを得ない状況に
既になっている。
旧ソ連時代の政策から、綿花栽培に力を入れるために上流に運河を建設したことから、急激に水量が減り始め、
現在では、1960年当時に比べて表面積で約20%にしか過ぎない。
実は私たちがコットン衣料を安価で入手できるようになった背景の一部である。
これが、先日の日記で触れたバーチャルウォーターという概念を我々が知らなければならない所以である。
我々の大量消費と使い捨てという生活文化をもっともっと見直す必要があるということ、リサイクルにある程度お金を必要として
その出費に関して責任を持つということは、少なくともバーチャルウォーターの輸入量の軽減と自然保護という観点で
我々の義務にするべきである。
そうでなくても今の我々を巡る水の状況は、水をいかに守るかということに大規模な資本投資をせざるを得ない状況に
既になっている。
Posted by きべいち at
09:19
│Comments(0)
2009年09月05日
ミヨリの森
http://www.eigaseikatu.com/title/s-19234
たまたまやっていたテレビでやっていた映画のタイトルです。
一人の少女が森の妖精達とダム工事のためにやってきた大人達との闘いの映画です。
森こそが生命の源の水を生かし巡りめぐってまた雨となって森に降る、だからこそ森を守るというメッセージがあったと思います。
一方でダムの工事のための大人にも『生活のために必要なんだ』と言わせてます。
先だっての日記で、日本の地形特性からダムによって水資源管理をして有効に配分しようとしてきた日本の水の状況を説明致しました。
このアニメの中のダム工事の大人達の『生活のため』というのは、恐らく工事によって生活が成り立っているということを説明し
いるのでしょう。
ですからここでいう水資源管理とは少し文脈が違うと思います。
ダムの問題の是非がいろいろ問題になっていますが、水を巡る日本の状況を見ていくと
我々の生活の中の水の関わり方もやはりきちんと見ていかねばならないですね。
たまたまやっていたテレビでやっていた映画のタイトルです。
一人の少女が森の妖精達とダム工事のためにやってきた大人達との闘いの映画です。
森こそが生命の源の水を生かし巡りめぐってまた雨となって森に降る、だからこそ森を守るというメッセージがあったと思います。
一方でダムの工事のための大人にも『生活のために必要なんだ』と言わせてます。
先だっての日記で、日本の地形特性からダムによって水資源管理をして有効に配分しようとしてきた日本の水の状況を説明致しました。
このアニメの中のダム工事の大人達の『生活のため』というのは、恐らく工事によって生活が成り立っているということを説明し
いるのでしょう。
ですからここでいう水資源管理とは少し文脈が違うと思います。
ダムの問題の是非がいろいろ問題になっていますが、水を巡る日本の状況を見ていくと
我々の生活の中の水の関わり方もやはりきちんと見ていかねばならないですね。
Posted by きべいち at
23:40
│Comments(0)
2009年09月03日
銀の食器
ちょっと水の問題は、一旦休止して何故昔の西欧の王侯貴族が銀の食器を愛用していたかを最近知ったのでちょっとご披露・・・
実は、これも水に関わる仕事で知ったことなのだけれど・・・
昔の西欧の王侯貴族達は、銀の食器をピカピカに磨いて使用していた。
我々はそれがステイタスの象徴ととるだろう。少なくとも僕はそう思っていた。
本当は、違うということ、その真実を知った。
何年か前に、映画で『薔薇の名前』というのがあった。原作はイタリア人作家・学者のウンベルト・エーコである。
その物語は中世の修道院で起こるなぞの連続殺人事件の謎を解くというもの。
その死因が砒素中毒によるものである。
最近では、和歌山のカレー事件で有名になった。なぜ日本の一般人が砒素などを扱うかも一緒に知ったのだけれど、それはさておき・・・
西欧の中世では、暗殺に一番使われる手段、毒薬として砒素が使われてきたらしい。
王侯貴族達は当然毒見をしなければならない。
日本の時代劇だと家来とかが味見をしていた。
西欧はどうか?
その時に力を発揮するのがピカピカに磨かれた銀食器なのである。
料理に砒素が混入されていると、ピカピカの銀食器はすぐに腐食し色が変化するということらしい・・・
文化はその成り立ちの謎解きをしなければ、理解できない典型的な例だ。
実は、これも水に関わる仕事で知ったことなのだけれど・・・
昔の西欧の王侯貴族達は、銀の食器をピカピカに磨いて使用していた。
我々はそれがステイタスの象徴ととるだろう。少なくとも僕はそう思っていた。
本当は、違うということ、その真実を知った。
何年か前に、映画で『薔薇の名前』というのがあった。原作はイタリア人作家・学者のウンベルト・エーコである。
その物語は中世の修道院で起こるなぞの連続殺人事件の謎を解くというもの。
その死因が砒素中毒によるものである。
最近では、和歌山のカレー事件で有名になった。なぜ日本の一般人が砒素などを扱うかも一緒に知ったのだけれど、それはさておき・・・
西欧の中世では、暗殺に一番使われる手段、毒薬として砒素が使われてきたらしい。
王侯貴族達は当然毒見をしなければならない。
日本の時代劇だと家来とかが味見をしていた。
西欧はどうか?
その時に力を発揮するのがピカピカに磨かれた銀食器なのである。
料理に砒素が混入されていると、ピカピカの銀食器はすぐに腐食し色が変化するということらしい・・・
文化はその成り立ちの謎解きをしなければ、理解できない典型的な例だ。
Posted by きべいち at
22:17
│Comments(0)
2009年08月24日
水について…
昨日は、日本の水を巡る状況が豊かであると感じる現状の概略を書きました。
そうではなく、日本が海外の水に大きく依存していると言われる現実も知るべきでしょう。
それは我々の近代的な生活に必要なものが、生産される過程において水を大量に使い、輸入されているということです。
小麦やトウモロコシ、綿の製品、木材…上げたらキリがありません。
それらの輸入品が生産される過程でどのくらいの水を使うのでしょうか?
それらの直接使うのではなく、生産された農業や工業製品に使われた水を『バーチャルウォーター』と呼びます。
この概念は、東京大学の沖先生が提唱されました。
検索するとすぐに引っ掛かると思います。
そうではなく、日本が海外の水に大きく依存していると言われる現実も知るべきでしょう。
それは我々の近代的な生活に必要なものが、生産される過程において水を大量に使い、輸入されているということです。
小麦やトウモロコシ、綿の製品、木材…上げたらキリがありません。
それらの輸入品が生産される過程でどのくらいの水を使うのでしょうか?
それらの直接使うのではなく、生産された農業や工業製品に使われた水を『バーチャルウォーター』と呼びます。
この概念は、東京大学の沖先生が提唱されました。
検索するとすぐに引っ掛かると思います。
Posted by きべいち at
08:49
│Comments(0)
2009年08月23日
日本の水、資源としての水
日本人が一日に使う水の量を皆さんご存知でしょうか?
国連では、一日一人当たり50ℓの水があれば、生活が可能としています。
人として最低の衛生的な暮らしをするためには、きれいな水が一日20ℓ必要とも言われています。
私たち日本人が使用している水は水道の蛇口から供給される水を使っていますから、トイレやお風
呂、洗濯も含めて、ほとんどの水は清潔な水です。
それを日本人は一日平均で330ℓ使っています。
ですから日本の水の環境は豊かと感じられます。
それは紛れもない事実でしょう。
年間降水量は平均で1700mmということも考え合わせると尚更です。
ところが日本の河川は、急流で河川の距離が短く、すぐに海岸まで届きます。
ということは、資源としての水を貯蓄する機能を川が有していないという特徴が挙げられます。
ですからダムが必要ということになりますね。
(脱ダム宣言を田中康夫氏がやっていらっしゃいましたが、それはダム建設に絡む利権構造に対してと解釈しています。)
今日は、ここまでにしてまた日本を巡る水の状況をレポートしていきます。
国連では、一日一人当たり50ℓの水があれば、生活が可能としています。
人として最低の衛生的な暮らしをするためには、きれいな水が一日20ℓ必要とも言われています。
私たち日本人が使用している水は水道の蛇口から供給される水を使っていますから、トイレやお風
呂、洗濯も含めて、ほとんどの水は清潔な水です。
それを日本人は一日平均で330ℓ使っています。
ですから日本の水の環境は豊かと感じられます。
それは紛れもない事実でしょう。
年間降水量は平均で1700mmということも考え合わせると尚更です。
ところが日本の河川は、急流で河川の距離が短く、すぐに海岸まで届きます。
ということは、資源としての水を貯蓄する機能を川が有していないという特徴が挙げられます。
ですからダムが必要ということになりますね。
(脱ダム宣言を田中康夫氏がやっていらっしゃいましたが、それはダム建設に絡む利権構造に対してと解釈しています。)
今日は、ここまでにしてまた日本を巡る水の状況をレポートしていきます。
Posted by きべいち at
12:09
│Comments(0)
2009年08月23日
久しぶりに・・・
書く事が嫌いな訳ではなく、むしろ好きなんですが、どうも画面に向くと構えてしまうんですね。
恐らく、ペンで書くことで育ち、後からタイピングを覚えているからでしょうね。
ワープロが最初の日本語の入力の出会いですから、かれこれ20年以上も経っているんですが。
最近は、『水』問題に随分と詳しくなりました。
今日は久しぶりのご挨拶と言うことで、ここ1年間世界の『水』問題に触れてきたことをこれから少しずつ書いて行きます。
恐らく、ペンで書くことで育ち、後からタイピングを覚えているからでしょうね。
ワープロが最初の日本語の入力の出会いですから、かれこれ20年以上も経っているんですが。
最近は、『水』問題に随分と詳しくなりました。
今日は久しぶりのご挨拶と言うことで、ここ1年間世界の『水』問題に触れてきたことをこれから少しずつ書いて行きます。
Posted by きべいち at
11:36
│Comments(0)
2009年03月08日
観光政策
多くの税金の使い道を間違っている中で、お門違いな使い方が目立つのは観光政策です。
多くは観光施策として、素材にばかり補助を出して、投資効果の少ないプロモーションをしている。
まず、お金をかけるべくは、流通の仕組みに対してである。
人と物の交流が始まれば、必然的に素材は向上せざるを得なくなる。
ちなみに空港と飛行機は単なる商品の一部を構成される素材のひとつであり、流通の仕組みではない。
それを勘違いして議論するから、お金の使い方を間違える。
日本でどれだけの無駄な空港が作られたか・・・
多くは観光施策として、素材にばかり補助を出して、投資効果の少ないプロモーションをしている。
まず、お金をかけるべくは、流通の仕組みに対してである。
人と物の交流が始まれば、必然的に素材は向上せざるを得なくなる。
ちなみに空港と飛行機は単なる商品の一部を構成される素材のひとつであり、流通の仕組みではない。
それを勘違いして議論するから、お金の使い方を間違える。
日本でどれだけの無駄な空港が作られたか・・・
Posted by きべいち at
23:24
│Comments(0)
2008年10月30日
CO2の削減効果について
昨日もこのことが話題になった。
CO2の増加が地球の温暖化の直接的な原因ではないという理論がにわかに盛り上がっている。
特にこの問題で乗り遅れた感がある日本の学者等が環境に対して日本主導の新たな枠組みを提言するべきだとの声も上がってきている。
恐らく、CO2の排出量が直接的な原因ではないだろうということは、概ね察しがつくことが多い。
例えば、JAL のパイロットがコックピットから撮った写真をあるところで見た。確かに20年前と比べるとシベリアや北極海の氷の量が明らかに減っている。
でも急激な変化はこの2~3年という。
いくらなんでも私たちの生活の変化はこの数年の間に極端な変化はしていない。
つまり他に要因がある可能性の方が高いのではないかと思っていた。
科学者によると温暖化の原因は、太陽の活動の変化がもたらすものが圧倒的に大きいという。
では、CO2の削減は虚構と批判すべきか・・・
全くの虚構であると断言する著名な学者もいる。
私は、経済活動が現代の人間の中心になっていると思っている。
時代を戻せば貨幣やシステムもいわば人工物。
それが全体のシステムの中で機能を果たせばそれは虚構でも何でもない。
その点で言えば、CO2の排出権取引に関して言えば、過度な消費社会になってしまった私たちの社会を経済の縮小無しに生活の変化をもたらす方策としては今の時点ではベストだと思っている。
むしろ、このようなアイデアを考え、実行に移す指導者がいる社会はすばらしいと言える。
情けないことに、日本は知の最前線にいる方々が、虚構と批判し(理論としては正しいかもしれないが、矮小な視野としか思えない・・・)具体的に指導力を発揮できないことだ。
CO2の増加が地球の温暖化の直接的な原因ではないという理論がにわかに盛り上がっている。
特にこの問題で乗り遅れた感がある日本の学者等が環境に対して日本主導の新たな枠組みを提言するべきだとの声も上がってきている。
恐らく、CO2の排出量が直接的な原因ではないだろうということは、概ね察しがつくことが多い。
例えば、JAL のパイロットがコックピットから撮った写真をあるところで見た。確かに20年前と比べるとシベリアや北極海の氷の量が明らかに減っている。
でも急激な変化はこの2~3年という。
いくらなんでも私たちの生活の変化はこの数年の間に極端な変化はしていない。
つまり他に要因がある可能性の方が高いのではないかと思っていた。
科学者によると温暖化の原因は、太陽の活動の変化がもたらすものが圧倒的に大きいという。
では、CO2の削減は虚構と批判すべきか・・・
全くの虚構であると断言する著名な学者もいる。
私は、経済活動が現代の人間の中心になっていると思っている。
時代を戻せば貨幣やシステムもいわば人工物。
それが全体のシステムの中で機能を果たせばそれは虚構でも何でもない。
その点で言えば、CO2の排出権取引に関して言えば、過度な消費社会になってしまった私たちの社会を経済の縮小無しに生活の変化をもたらす方策としては今の時点ではベストだと思っている。
むしろ、このようなアイデアを考え、実行に移す指導者がいる社会はすばらしいと言える。
情けないことに、日本は知の最前線にいる方々が、虚構と批判し(理論としては正しいかもしれないが、矮小な視野としか思えない・・・)具体的に指導力を発揮できないことだ。
Posted by きべいち at
21:45
│Comments(0)
2008年10月04日
中山前国土交通大臣
議員活動を引退されるようですね。
日教組批判は大臣を辞しても尚変えるつもりは無いと言うなら、そのことを旗色鮮明にして選挙に出るのが政治家としてのあるべき態度だと思うのですが。
また日教組批判をするのなら、万事物事は両面あるわけですから、その両面が何であるか表現した上でどう解決に導くのか、それを表現しない限り政治家とは言えませんよね。
まあそういう政治家としての資質が欠けているんだと言う認識の下に引退されるのなら賢明ということでしょうか。
私は、日教組の味方でも何でもないです。日本の教育の問題は日教組でもアメリカでもその要因はないと考えていますから。むしろ教育をかくあるべきという考えがはっきりしないまま、現状への憂いを日教組やアメリカへの批判ばかりしている今の日本人達の心の問題だと思っています。
日教組批判は大臣を辞しても尚変えるつもりは無いと言うなら、そのことを旗色鮮明にして選挙に出るのが政治家としてのあるべき態度だと思うのですが。
また日教組批判をするのなら、万事物事は両面あるわけですから、その両面が何であるか表現した上でどう解決に導くのか、それを表現しない限り政治家とは言えませんよね。
まあそういう政治家としての資質が欠けているんだと言う認識の下に引退されるのなら賢明ということでしょうか。
私は、日教組の味方でも何でもないです。日本の教育の問題は日教組でもアメリカでもその要因はないと考えていますから。むしろ教育をかくあるべきという考えがはっきりしないまま、現状への憂いを日教組やアメリカへの批判ばかりしている今の日本人達の心の問題だと思っています。
Posted by きべいち at
10:02
│Comments(0)
2008年09月26日
イノベーション・クーリエ
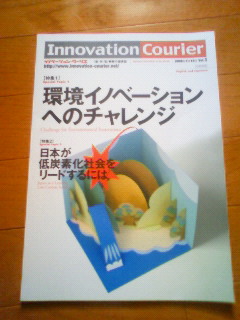 大変ご無沙汰をしておりました。
大変ご無沙汰をしておりました。この数ヶ月、新しい仕事の立ち上げに関わっており、そちらに集中しておりました。
あまり器用ではないのでひとつの事に集中し始めると周りに気が付かないという事がままあります。
さて、その新規事業とは?と言う事ですが、それが標題の『イノベーション・クーリエ《Innovation courier》』です。
イノベーションは、もちろん『改革、変革』と訳しますが、科学技術の世界では『技術革新』を意味します。
つまり日本の産業界の閉塞的な状況をイノベーションによって世界での産業、ビジネスをリードして行こうと言うことです。
現実に即して考えますと、日本は創業が古い大企業がありますが大企業は大企業を支えるパラダイム(枠組み、仕組みを作っている考え方)によって既得権を守ることが優先されます。
そうしますと新しい技術や人材が必ずしも日本の中で育たないということにもなります。
こうした現状が日本全体で閉塞的な状況を作り出してる要因と考えられます。
結果として国力の減退、ひいては生活の不安になります。
より活発な社会(経済や生活においても)を作るために眠っているイノベーションをプロデュースしていく作業、それがイノベーション・クーリエの役割なんです。
実は科学技術に関しては全くの門外漢でしたが、何事も新しく作り上げる作業は楽しいですね。決して楽ではありませんが…
2008年06月18日
リスクアセスメント
リスクアセスメントという言葉は皆さんご存知さろうか?
もともとは化学薬品等の毒性の人体リスクを評価する時に使われていた用語ですが、最近は事業コンサルタントにも使われるようになっています。
格段難しいことではなく、普段からも皆さんが新規に何かを立ち上げるとき、特に新規事業の立ち上げの時には必ずしているはずです。
つまり、事業を開始・継続の中でその事業のリスク事前評価をすることです。
そのリスク評価に従って、戦略を組み立てて行く訳です。
世の中の公共事業に関して、なぜかこのリスクアセスメントがきちんと行われてないことがあまりに多いような気がする。
税金を使ってやるから尚更必要なことなのに。
リスクアセスメントがきちんと行われないとちゃんとした戦略が立たない、ということは無駄が目立つということになります。
国民にとっては搾取されている印象にしか見えない。
静岡県民にとって例えば富士山・静岡空港はどのように見えるでしょうか?
この事業もきちんとしたリスクアセスメント無しに進んだ事業ですね。推進派でさえ、きちんとした戦略と立てていない。
リスクを項目立てて訴えれば、それが反対しているとしか取らない人々の多さ。
考えちゃいます、いろいろと・・・
もともとは化学薬品等の毒性の人体リスクを評価する時に使われていた用語ですが、最近は事業コンサルタントにも使われるようになっています。
格段難しいことではなく、普段からも皆さんが新規に何かを立ち上げるとき、特に新規事業の立ち上げの時には必ずしているはずです。
つまり、事業を開始・継続の中でその事業のリスク事前評価をすることです。
そのリスク評価に従って、戦略を組み立てて行く訳です。
世の中の公共事業に関して、なぜかこのリスクアセスメントがきちんと行われてないことがあまりに多いような気がする。
税金を使ってやるから尚更必要なことなのに。
リスクアセスメントがきちんと行われないとちゃんとした戦略が立たない、ということは無駄が目立つということになります。
国民にとっては搾取されている印象にしか見えない。
静岡県民にとって例えば富士山・静岡空港はどのように見えるでしょうか?
この事業もきちんとしたリスクアセスメント無しに進んだ事業ですね。推進派でさえ、きちんとした戦略と立てていない。
リスクを項目立てて訴えれば、それが反対しているとしか取らない人々の多さ。
考えちゃいます、いろいろと・・・
Posted by きべいち at
11:10
│Comments(2)
2008年05月26日
松崎町の合併問題
2度の議会での否決、今度は住民投票・・・
一概に行政や町長を批判できない事情があるかもしれません。
皆さんはこの件をどうのように見ていらっしゃるのでしょうか?あるいはお考えでしょうか?
そもそも合併をなぜ推進するようになったのでしょうか?
実は行政規模としては、一万人くらいが一番目が届きやすいと聞いたことがあります。
もう一度皆さんでこの合併問題考えたいですよね。
一概に行政や町長を批判できない事情があるかもしれません。
皆さんはこの件をどうのように見ていらっしゃるのでしょうか?あるいはお考えでしょうか?
そもそも合併をなぜ推進するようになったのでしょうか?
実は行政規模としては、一万人くらいが一番目が届きやすいと聞いたことがあります。
もう一度皆さんでこの合併問題考えたいですよね。
Posted by きべいち at
12:14
│Comments(7)